本稿は筆者Bearringの寄稿になります。
留意事項等は下記リンクページをご参照ください。
問1
(1)
⑬赤外画像で白いことから、雲頂高度の()が低いとあることから、「温度」
(2)
これはわかりやすいところから書いていきましょう。
コツは北側の1008hPaの等圧線と南側の1012hPaの等圧線の間に、低気圧を囲う1008の閉じた等圧線と高気圧を囲う閉じた1012の等圧線があることを最初に認識することです。
そして1010の線を引くとき、必ず右手側には1010超の、左手側には1010未満の値しかないことを確認しながら引きます。
まずわかりやすい西側の端から。
この2つの線の真ん中あたりが1010の線になります。そこから東に伸ばしていくと点Bが1010ですのでここを通ります。
そのまま東に向かうと、点Dが1008ですから、これは1010の上側(左手側)に来ないといけません。
つまりここで南に大きくカーブします。カーブした先には点Aの1010がありますのでここを通ります。
付近に低気圧の閉じた等圧線があります。ここは1008と1012の間に当たるため、1010はこの間を通ります。
低気圧の北側を通ると1008と1008の間に1010の等圧線が1本だけになるのでおかしなことになります。
閉じた等圧線を通ると、GとHがあり、それぞれ1010超ですから、これは右手側に入れなければなりません。
ここで大きく1010の線を北上させることになります。
そのまま高気圧の閉じた1012の線を通り、南側に進み、東側の枠線までつなげます。
相当ゆがんでいる線ができますが、「必ず右手側には1010超の、左手側には1010未満の値しかないことを確認しながら引く」という原則通りに行えば短時間で解答可能です。
(3)
強風軸解析です。
衛星画像では複数の暗域があるため、300hPaの天気図から解析し、解析後に水蒸気画像で確かめます。
300hPa天気図には等風速線がありますので、等高度線の曲がり方を参考にしつつ、等風速線の楕円の縁通すように線を引きます。
(4)
①
上記の強風軸をトレーシングペーパーに写し取り、水蒸気画像に重ねると、暗域の西の端に重なります。
要は強風軸の東側に暗域があります。
暗域は中上層で乾燥しており、寒気側の大気です。
強風軸が暖気側と寒気側の境目を通っており、暗域は寒気側の端っこで、下降流があるところです。
ジェット気流が南に蛇行すると、低気圧側は傾度風の原理で、低気圧性曲率の大きなところは風速が遅くなり、速度収束します。その結果余った空気が下降流となります。
これが低気圧を発達させることになります。
話はそれましたが、ジェット気流の東側(寒気側)に暗域が広がるのは上記の通りですので、位置関係は「すぐ東側にある」となります。
解答例の「南北に伸びている。」というのは偏西風の蛇行が大きいということを示すためについているものと思われます。
位置関係を問われているため、走向まで書ける方がどれくらいいるのかとは思います。
②
暗域Qは正渦度域の北側の渦度0線付近にあります。
細長い正渦度域では上昇流が起きているわけですから、相対的に中上層は周囲よりも湿っているはずです。
暗域は中上層で乾いているわけですから、この正渦度域にはできず、そのすぐ北側に対応しています。
この問題で解答例と全く同じ答えを書くのは難しいと思います。
位置関係の問題は見たままを書くということを心がけましょう。
(5)
積乱雲の位置と暗域の関係ですが、両方とも暗域の周辺にあります。
そもそも暗域は乾燥しているため、水蒸気量が少なく、中上層で相当温位が低いエリアに当たります。
これは上層に向かうにつれて相対温位が減少する「対流不安定」に当たりますので、暗域付近では発達した積乱雲ができやすい環境となります。
よって、雲域と暗域が接しているという解答はこの原理と矛盾しません。
問2
(1)
エマグラム、SSIの基本ですね。
(2)
いかにうまく短時間で作図をするかにかかっています。湿潤断熱線の間隔は上層に行くにつれてどんどん広がっていくため、
持ち上げ凝結高度の点が295と300の湿潤断熱線の間を大体1:6で按分する点にあることを定規で見つけ出し、最上層の200hPaのところに同じ比率で点を打って、その間を緩やかなカーブでつなげるという方法が早く、かつそこそこ正確な線を引くコツだと思います。
目分量ではなかなか難しいと思います。
(3)
これは地表の温度を仮に30度としてエマグラムに書き足してみるとわかります。
持ち上げ凝結高度は高くなりますが、自由対流高度は低くなり、平衡高度は高くなります。
自由対流高度が低くなるため、対流は起きやすくなります。
問3
(1)
①②これは見つけて線を引き、はかるだけですね。
時刻は12時間で進むうちのおよそ4割の地点に140度線がありますので、約5時間後です。
③
図1で佐渡にあった低気圧の南東部分が出っ張っているため、ここは気圧の谷です。
基本的に等圧線が不自然に曲がっているところには何らかの擾乱があるものです。
よって等圧線の値を示し、低気圧中心の南東側にこの線で囲まれた領域が広がっていることから、新たな低気圧が発生しかけていることを指摘します。(発生状況)
(2)
問1の(5)で指摘した細長い正渦度域の北側に沿って暗域がありますので、この正渦度域が南下すれば暗域も南下するものと考えてよいと思います。
問4
(1)
①
図8と9を見ると、北東風が山地の北東斜面にぶつかっていると思われますので、それを指摘します。
②
北東(北北東)の風と南寄りの風がぶつかっていますので、風が収束していることを示す必要があります。
(2)グラフの読みとりですので特に問題ないと思います。
(3)
このパターンの問題の場合、答えはおおよそシア―ラインの両サイドの気温が違うパターンか、積乱雲による冷気外出流になります。
今回はシア―ラインの両サイドで気温の差がそこまでなく、一般場の風によって気温が21.9度まで降下することは考えられません。
よって冷気外出流の影響となります。

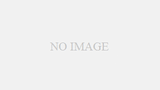
コメント