ヤフーのニュースを見ていると、タイトルのような記事が見受けられた。

不動産評価がニュースになることは、近年それなりに見受けられているため(有名なところでは、森友学園、富士急の賃料問題、晴海フラッグ評価など)評価する側もそれは心得ていると思うが、このような事案があると、なぜそうなったのだろうと背景を知りたくなる。
多くの事象においては、鑑定評価書の条件を踏まえると、評価者としては妥当な作業を行ったという形に帰着することもあるのだが(その条件設定自体が公共の評価として妥当ではないという可能性はもちろんある)、記事の内容が真実であれば、これはそうではなさそうだ。
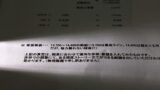
これは不動産鑑定士が行った鑑定評価かどうかは不明ではあるが、鑑定評価であれば、提示した価格が大きく変わるようなことはたとえドラフトからの変更であったとしても合理的な理由が必要であろう。
また、一部を造成地として判断する修正をしたために前提が変わったという主張であるが、高々3000平方メートルに満たない当該土地の評価において、実地調査を行っておいてそれが当初評価時に分からなかったということはまずありえないだろう。
また、もし、仮に造成部分が高い評価だとしたら、それまでは固定資産税評価額はどうなっていたのだろうか。所有者が所有する土地の価値に見合った税負担はされていたのだろうか。低い固定資産税負担で評価されてきた土地を、売買の時にそれまでとは異なったロジックで評価してほしいと依頼し、高い価格で買い受けたのであれば、自治体内部で当該土地に対する価格形成要因の判断を、円滑な買取を行うために無理やり捻じ曲げたことにならないだろうか。
用地補償は通常の売買とは異なる。どうしても欲しい土地を買いたいということは、不動産は同じものが二つとなく、代替が効かない資産であることから、それは起こりうるものである。
ただし、用地補償とは税金を使って行うものであり、税金を使うということは、利益の配分を行っていることに他ならない。本来であればみんながなるべく公平に恩恵を受けるべき税の使い道を、不当な評価が行われた場合には、当該評価により利益を得るものに過大に配分されることになってしまう。
そのために評価・補償の専門家がおり、各種の基準が整備されているわけであるから、評価担当者はこれを理解したうえで無理な依頼者からの要望があれば、それは毅然とした態度で断るべきである。
それが専門家としての最低限の誠意であると考える。みんなが断るのであれば当該評価額は実現しないのだから。


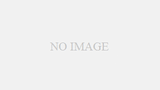
コメント